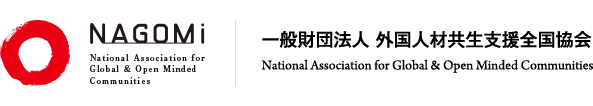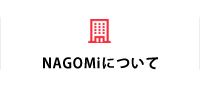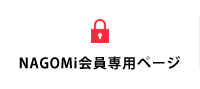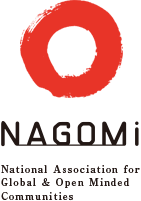グローバル人材共生の政策に関わる実務者、識者らの政策インタビューの第19回は、自民党の外国人材等に関する特別委員会事務局長の鈴木英敬衆議院議員から、外国人材受入れの基本的な考え方と外特委の役割などについて聞きました。鈴木氏は三重県知事時代、みえ外国人相談サポートセンター(MieCo)を設立するなど外国人材受入れの先進的な自治体のトップとして政策遂行にあたってきました。
三重県知事時代、みえ外国人相談サポートセンター(MieCo)設立等で支援体制充実
―外国人受入れの基本的な考えを聞かせてください。
鈴木議員 三重県で知事をやっていましたので、地方でも人材不足が深刻化し、国際的な人材獲得競争が激化する中で、日本が外国人材から「選ばれる国」になるためにどうしたらいいかということを考えてきました。「選ばれる国」になるためには、我が国で働くことや暮らすことが魅力的だと感じてもらう環境づくりが大事です。魅力的ということを因数分解していくと、快適であることとか安心であることとか自分の希望が叶うことではないかと思います。
三重県知事の時代に多文化共生の指針を策定しました。平成30年度調査では、公立小中学校における日本語指導が必要な外国人児童生徒の在籍率は全国で1位、で使用言語も27と多かった。そこで日本語教育の推進計画を策定するとともに、みえ外国人相談サポートセンター(MieCo)を設立し、多言語での支援体制を充実させていきました。防災対策におけるひらがなを用いた情報発信なども取り入れ、外国人と日本人双方の安心感と信頼感を醸成する基盤を築いていきました。コロナ感染対策における外国人材への情報発信などMieCoに特別の相談窓口をつくって対応させていただきました。

外国人材受入れは「共生」「厳格さ」「産業政策」の観点から制度設計が必要
―自民党外国人材等に関する特別委員会の事務局長としての抱負は何ですか。
鈴木議員 知事時代に「共生」についてのさまざまな施策を実行してきました。国会議員となり、国として外国人材受入れの基本的な考えは「共生」と「厳格さ」をバランスよく両立することだと思います。外国人と日本人が互いの文化や背景を理解し、共に快適で安全に暮らせる社会を築く「共生」と同時に、法令違反には厳しく対応する「厳格さ」で、全体の信頼を守る仕組みを整えることが求められています。 特別委員会の山下貴司委員長からは、「共生」と「厳格さ」に加えて、私が経済産業省出身なので、特に産業競争力や企業経営の向上に資する「産業政策」の観点から外国人材の制度設計に向けて取り組んでほしいと言われています。働く場での公平な待遇や人権尊重の確保、地域社会での生活環境を整備すると同時に、法令違反については厳しい対応をしなければいけません。また産業別に求められる人材の特性を把握し、量的な確保と質の向上を両立させる政策も重視されます。特別委員会の名称が外国人労働者等特別委員会から外国人材等に関する特別委員会に変更になりましたので幅広い視点でやっていきたい。 令和7年(2025年)は、特定技能・育成就労制度に関する基本方針、分野別運用方針などの具体的施策の検討、関係省令、日本語試験や技能試験など現場に直結する制度設計が進む正念場の年になりますので、事務局長の重責を果たしていきたいと思います。

基本法のような国家の背骨になる理念や基本方針は重要であると認識
―NAGOMiは外国人材を単に労働者としてではなく生活者として受入れる理念に基づく外国人材共生基本法(仮称)の制定が必要だと提唱しています。
鈴木議員 党としては、政府が制度改正の施行までのロードマップを作成しているので、そうした制度設計が着実に進められるようにしていくと同時に、外国人材受入れを幅広く支える「基本法」についてもNAGOMiの提言をはじめ、いろいろな意見を伺っていきたいと思います。細かい制度もさることながら、国家の背骨になるような物事の軸になるような基本法というのは大変重要であると考えています。自分は知事時代に外国人に限らず、理念に基づくさまざまな条例をつくってきました。三重県中小企業・小規模企業振興条例は、国の小規模企業振興基本法よりも前につくりました。基本法のような背骨となる理念や基本姿勢は大事だと認識しております。
鈴木英敬(すずき・えいけい)衆議院議員
三重県第4区。当選2回。経済産業省から三重県知事(3期)を経て、内閣府大臣政務官、自民党文部科学部会副部会長などを歴任。現在は党選挙対策委員会副委員長。50歳。